リスク・レジリエンス工学
研究群紹介
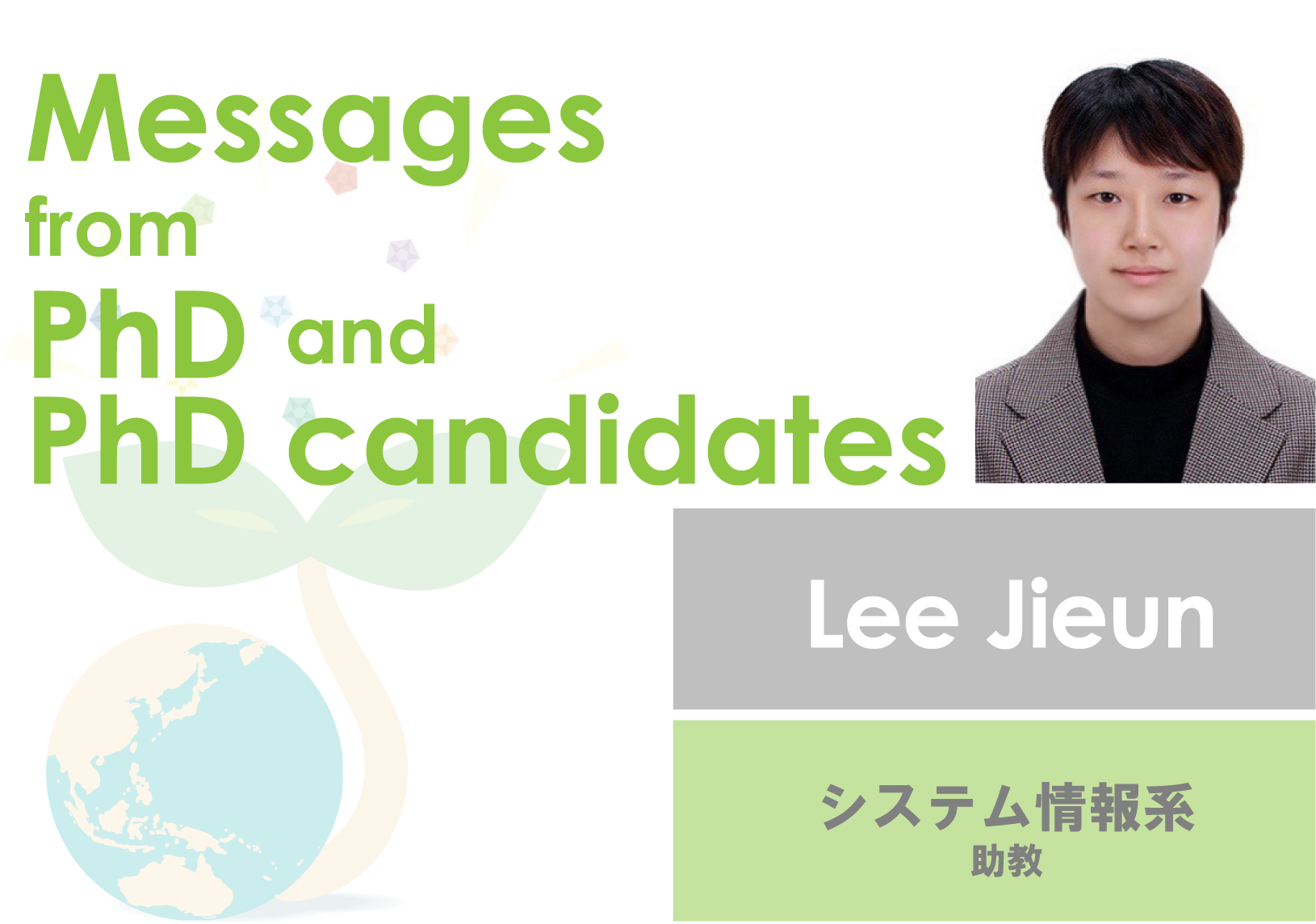
Messages from PhD and PhD candidates 2021 Vol.7 Lee Jieun 氏(システム情報系助教)
今回は、「Messages from PhD and PhD candidates 2021」と題し、博士後期課程の現役学生・修了生に進学の経緯やご自身の研究、今後の展望などについてお話を伺います。
シリーズ7回目は、2020年9月にリスク工学専攻を修了して学位を取得され、現在は筑波大学 システム情報系 情報工学域の教員としてご活躍されるLee Jieun先生にご登場いただきました。
Lee先生が博士後期課程への進学を視野に入れた時期は、いつ頃だったのでしょうか?
私は学類生の時から博士後期課程に進学しようと考えていました.その当時は研究が何かも知らず,ひたすら「博士になりたい」と考えていました.研究室配属後から,本当に自分が研究に向いているか,また,これを続けられるか悩みましたが,今まで発見されてない何かを生み出し続ける研究のプロセスは好きでした.それからは単純に考えるようになって,研究を続けないと,博士後期課程に進学しないと未練が残るだろうと思い,進学を決めました.
博士後期課程時代の研究テーマについて、教えていただけますか?
私の博士後期課程時代の研究テーマは,「監視制御下での自動化機械に対する人間の信頼感」でした.
近年,自動運転などの一般の人々が使える自動化が実現されておりますが,これらの自動化システムはまだユーザの監視制御を求めています.そのため,機械における十分な知識を有してない状態では,技術に対する人間の信頼感が十分に醸成されない恐れがあります.
信頼感は,自動化機械に対するユーザの行動・態度・使用の意向や有無に大きく影響する心理要素であり,この信頼感を考慮したヒューマンマシンシステムのデザインが期待されております.機械に対する人間の信頼感は,過去20年以上にわたって研究されてきました.これらの研究は,Muir & Moray (1996) の研究を踏まえていると言っても過言ではありません.Muir & Morayは,人間-人間の信頼感の醸成プロセスをシステム-人間のコンセプトに適用し,その理論を監視制御システムの下で実証した記念的な研究です.この研究は,人間の信頼は,Dependability,Predictability,Faithの3つの次元からなるものと定義しており,機械に対する豊富な経験を積んでない非熟練者の信頼がどのように醸成されるかをこの3つの次元を使って論じています.
私の研究は,監視制御を求める自動化システムとのインタラクションにおいて,初期段階の信頼感を支配する要因を把握し,その支配要因をシステムデザインに活かすことを目指しました.まず,Muir & Morayの実験を再現し,自動化システムに全般におけるユーザの信頼感が形成される過程とその次元を明らかにし,過去の知見が時代や文化的背景によらない一般性を有するものであることを明確にしました.また,このレプリケーション実験から得られた知見をレベル2の自動運転システムに応用して,他の自動化システム分野に対する信頼モデルの拡張性を検証しました.具体的には,監視制御を求める自動運転システムにおいて,自動運転車に対する事前知識やシステムの性能によって運転者の信頼感を支配する要因が変化しうることを観測しました.さらに,運転者の個人属性を考慮した分析を通じて性別・年齢・職業による信頼感の違いを示しました.
博士後期課程時代に楽しかった出来事、印象的だった出来事などがあれば、お聞かせください。
私の研究生活にポジティブな刺激になったのは,国際学会参加だと思います.頑張ってプロシーティングを書いて,アクセプトされたからもらえるご褒美みたいに考えられるかも知れませんが,学会でしか味わえない雰囲気,また,優秀な研究者の講演は良い刺激になったと思います.
また,博士後期課程の間はストレスで眠れない日が続きました.ストレス発散の重要さを感じ,ダンスを始めました.週に3, 4日は必ずダンスの時間を設けて,1時間は頭の中を空っぽにしてリフレッシュしました.それがきっかけで,ダンスは今も楽しく続けております.
学位を取得された後、どのような経緯で現職の道に進まれたのでしょうか。また、現在の大学でのお仕事について、教えてください。
私はアカデミアに残る気で博士後期課程に進学したわけではなかったので就活も行いましたが,国際学会への参加や学生指導を積み重ねて「大学でしかできないこと」をやってみたいと思うようになりました.
2020年9月に学位を取得し,10月から慶應義塾大学の理工学部で特任助教としてNEDOの委託研究を行いました.慶應義塾大学では,自動運転の社会実現を目指した研究に集中して実験の設計や実施,論文執筆を行ってきました.2021年7月からは,助教として筑波大学に戻ってきており,スーパーグローバル大学事業の科目ジュークボックスシステムのマネジメント,研究室でのゼミ参加・学生指導,学内の会議参加,また,自分の研究を行なっています.また,現在も慶應義塾大学の特任助教として兼業しています.
博士後期課程でのどのような経験が、現在の仕事に活かされていると感じていますか?
博士前期課程までは自分が抱えているお仕事の量がそこまで多くなかったので,時間をマネジメントするという概念が自分の中ではっきりしていませんでした.博士後期課程に進学し,専攻のTA活動,研究指導,また,自分の研究を進める等,限られている時間の中で様々なタスクを上手に管理しないといけない状況を迎えました.その中でも,最も辛かったのは,卒業要件を満たすことでした.私の場合,卒業要件のジャーナルペーパーが中々通らず,がっかりの2.5年を過ごしました.リジェクトが何回も続いて,最後の最後に奇跡的にアクセプトをもらって学位審査を申請できる要件を満たしました.
私はまだ博士号を取ってから1年程度しか経ってない素人なのですが,博士後期課程は,一人前の研究者になるための修業だと思います.研究者は,誰かに認めて頂かないとその価値を証明できないので,業績を積み上げていかなければなりません.これらの失敗は,長期的に私を成長させた大きな経験だと考えております.リジェクトの経験は辛く,自分の研究が否定されるような気もしました.最初のリジェクトから立ち直るまで,1年がかかりました.次は6ヶ月,その次は3ヶ月,その次は1ヶ月.凹んでいても解決策は見つからないので,合理的な批判であることは素直に受け止めて,貫くべきことに関してはきちんとしたエビデンスを持って主張することが大事であることがわかりました.
この経験のおかげで,今自分がやらなければならないことの優先順位をはっきりさせて,それを達成するためにどう時間を管理していくべきか,即ち,タイムマネジメントと繋がることがわかりました.これは,雑誌論文だけではなく,業務・研究費の採択・就活等にも通用する話だと思います.このタイムマネジメントにおける自分なりの哲学は,これから私が経験する予定の様々な失敗を乗り越えるために適用できるのではないかと思います.
Lee先生の現在の研究テーマについて、教えていただけますか?
私は,博士後期課程でまとめた「人間の信頼感のモデル」を他の自動化システムに適用し,それを活かしたヒューマンマシンシステムデザインを研究しています.システムデザインの提案と検証を通じて,信頼モデルの拡張性と補完を考えております.具体的には,パネルやライトを介して自分の意思を伝達するインタフェースを装着した自動運転車と交通参加者の間のインタラクションの場面を想定していて,信頼モデルを適用してインタフェースを構築し,いかに交通安全と効率に寄与するかを考えています.
研究関心の原点についてお伺いしたいのですが、これまで取り組まれてきた研究テーマに関心を持つきっかけは何だったのでしょうか?
私の研究は,「人間の信頼感」に着目しています.「博士後期課程時代の研究テーマ」のところで説明した通りに,1980年度末に行われた機械に対する人間の信頼感の始祖となるMuir & Morayの研究があり,私の研究は,それをレプリケーションして現代のコンテキストを考慮して再解析しました.Muir & Morayの研究は,信頼感はPredictability, Dependability, Faithで構成されていると主張していて,Predictabilityから信頼感が芽生え始めると想定しました.しかし,実証実験を行ったところ,初期段階の信頼感を支配する要因はFaithであることが観測されました.
自分の指導教員である伊藤誠先生からMuir & Morayの研究を紹介して頂いたとき,彼女らはFaithが初期の信頼感を支配する要因であることが予期せぬ結果だと言っているが,よくよく考えるとこの結果は当たり前なことだと,「信じないと何も始まらない」と仰いました.私はその一言に感銘を受け,信頼感の研究を始め,現在まで続けております.
ご自身の博士後期課程でのご経験やこれまでのキャリアを振り返り、今、博士後期課程への進学を考えている後輩の皆さんにメッセージをいただけますか?
私は,自分がこれから抱えていかなければならない未練の有無をもって選択を続けてきました.ある種,脳に虐待をする程度まで考え続けても,結局,心が働く方向に向かって進路を決めてきたと思います.何を選ぶとしても後悔は不可欠ですので,未練が残りそうだったら進学すべきであり,その後はがむしゃらに貫くべきだと思います.信じないと,何も始まらないです.



