構造エネルギー工学
研究群紹介
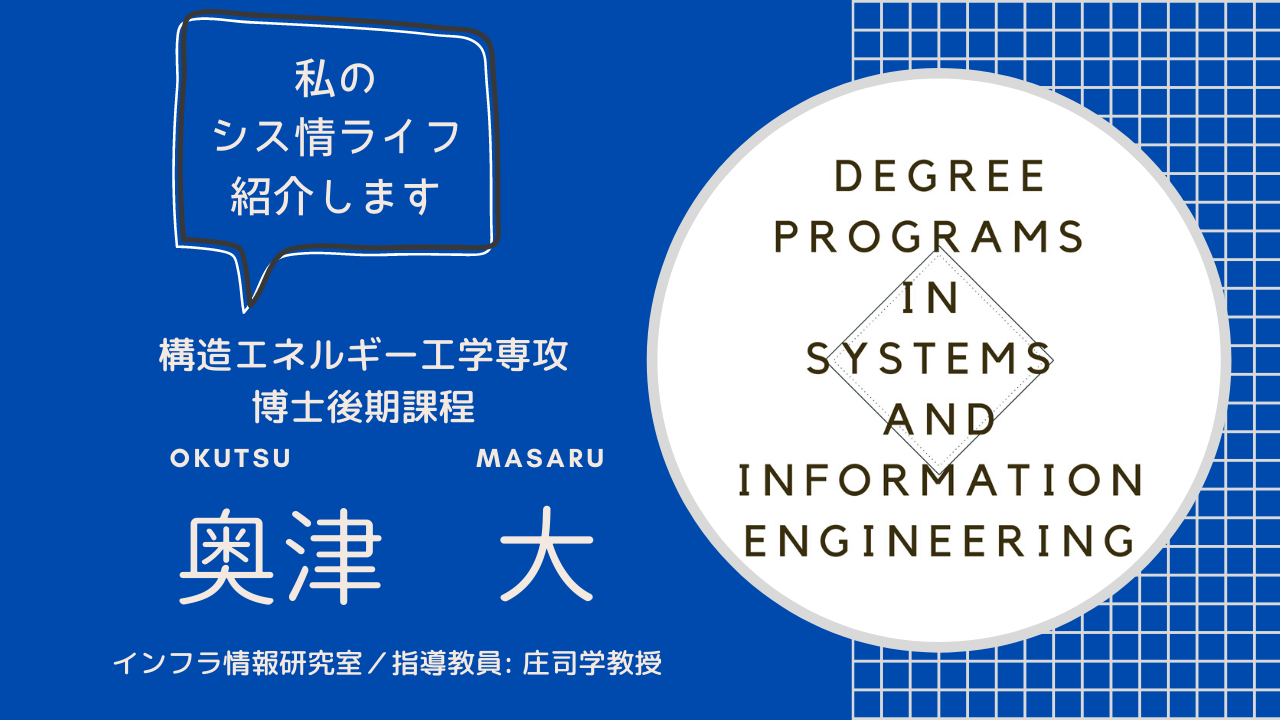
シス情在学生インタビュー企画 Vol.7: 奥津 大さん(構造エネルギー工学専攻)
システム情報工学研究群(通称:シス情)では、在学生に大学院での研究のこと、授業のこと、そして筑波大での生活についてリアルな声を聞くインタビュー企画を行っています。
第7回目となる今回は、構造エネルギー工学専攻(今年4月より構造エネルギー工学学位プログラムに改組)博士後期課程に在籍する社会人学生の奥津さんにお話を伺いました。奥津さんは、私たちの社会を支える地下管路(電線や光通信などのケーブルを地下に埋設するための管)の耐震技術の研究に取り組んでいます。
まずは、社会人として学位取得を目指されたきっかけ、そして現在の研究室(インフラ情報研究室)を選んだ理由について教えてください。
業務上、庄司学先生にご指導をいただいていて、学位取得にチャレンジすることを勧められたためです。また、上司が先生のもとで学位取得にチャレンジし、見事取得されたことに触発されました。
筑波大学が職場から近い(徒歩30分、自転車15分)ことも理由の一つです。
受験前、研究室にはどのようにコンタクトを取りましたか?
上述した通り、先生とは業務上でご指導をいただいていました。社会人のための博士後期課程「早期修了プログラム」説明会にも参加し、興味が深まりました。
奥津さんの現在の研究テーマについて教えていただけますか?
地下管路の劣化の定量化とそれを考慮した耐震性評価に関する研究です。
地下管路は、見えませんが社会を支える重要な設備です。見えないので被災するとその場所の特定や補修が大変です。現在の研究を通じて、このような課題の克服に少しでも貢献したいと思っています。

▲熊本地震(2016年)で被災した管路

▲熊本地震後の現場調査状況(本人左)
災害時の地下管路について関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか?
大学院生の時に兵庫県南部地震が発生し、ライフラインの地震工学に興味を持ちました。幸い就職してから長期間、主に地下管路の耐震技術の開発に従事することができました。神戸、鳥取、新潟、宮城、岩手、熊本、北海道など各地の被災地で調査をしてきましたが、毎回地震のエネルギーに圧倒されます。地震の発生を止めることはできませんが、少しでも被害を軽減し、復旧・復興を早めることはできないか、という思いがモチベーションになっています。
次に授業についてですが、今まで履修した授業の中で特に面白い!と感じたものはありますか?
せっかく大学院に入ったので、専門分野以外を履修しようと思い、大学院共通科目「UT-Top Academist’s Lecture 」を履修しました。毎回異なる多彩な分野の先生方の講義は、大変興味深かったです。また学生さんの質問がとてもユニークで、その発想力に感心しました。学生さんの時には突拍子もない質問への先生方のお答えも、ユーモアがありながらも考えさせられるものが多くありました。
奥津さんは社会人ドクターでいらっしゃいますが、研究と業務の両立に苦労された点はありますか?
入学願書提出前から、上司と「業務優先」ということを約束していました。入学後は、上司も授業日程に配慮をしてくれましたが、外せない会議や出張もあり出席日数が足りずに取得できなかった単位があります。大学院セミナーでは、欠席した社会人が後日発表者と質疑応答をすることで救済される仕組みがあり、とても助かりました。
学位取得後の業務やキャリアについて、現時点でお考えのことがあればお聞かせください。
今までの20数年の研究者としての総仕上げとして学位にチャレンジしていますが、やっている中でまだまだ未熟だと感じる点も多々あり、また新しくやってみたいと思うこともでてきました。学位を取得したとしてもゴールではなく、通過点として今後も研究に取り組んでいきたいと思います。
最後になりますが、今、シス情の受験を考えている皆さん(特に社会人の方)に、何かお伝えしたいことがあればどうぞ!
大学院生活で感心したのは、若い学生さんたちが真剣に研究をしている姿です。また彼らの1年間での成長が素晴らしく、まぶしく感じるとともに刺激を受けました。
先生からは、職場の上司・同僚とは異なる研究者の視点から、厳しくも温かいご指導をいただいており、亀のごとき歩みではありますが、成長できているのではないかと思っています。
関連リンク
- 構造エネルギー工学学位プログラム:http://www.eme.tsukuba.ac.jp/



